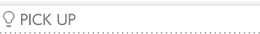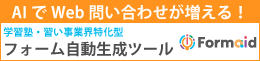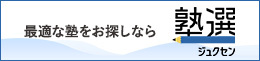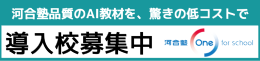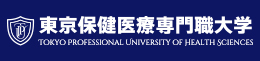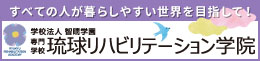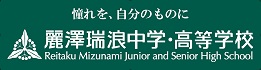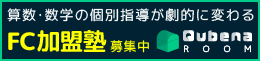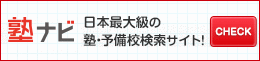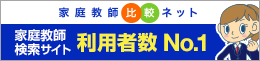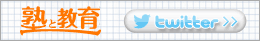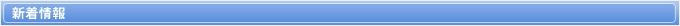
AJC(全国学習塾協同組合)森貞孝理事長の最新教育情報 第56回
教育の何をどうすればいいのか、世論を盛り上げよう
昨年の出生数は過去最低の84万2897人と発表になった。令和2年に初めて90万人を割って、87万人台に落ちてさらに下降線を辿っている。今年か来年には70万人台へ減少しそうな勢いだ。既報の通り中国や韓国でも少子化に歯止めが効かないが、ヨーロッパの諸国は同じ少子化でも緩やかに見える。ハンガリーのような極端な少子化対策をして一気に2割近くも増えるなどといった対策をしなくても、そこそこに落ち着いているように見える。
ロシアがウクライナに侵攻した。ロシア側の論理で非武装化・中立化などを求めて力でねじ伏せようとしている。力でねじ伏せるやり方は、アメリカのアフガニスタンやベトナムでの失敗が示す通り最終的には思い通りにいかない場合が多い。それにしてもウクライナ国民の悲惨さに心が痛む。この記事が目に触れるころには事態が好転してくれることを祈りたい。
前号でお伝えした通り、教育立国推進協議会は総会と各分科会に分かれて積極的に動き出した。第3回総会では教育国債など教育に積極的にお金をかけて国力を伸ばしていくフランスのサルコジ国債など世界各国の対応が紹介され、OECD諸国の中でGDPに対する公財政支出の割合が平均よりもかなり低いことに衝撃を受けた。日本では教育は親の責任として放置されてきたが、このままではいけないと痛感した。さらに第4回総会で、義務教育の不登校が19万6000人に達していることは承知していたが、長期欠席児童が約29万人もいることにも驚いた。
子どもが不登校になると親は子供の悩みや世話で仕事をやめたり、正社員からパートに勤務を変えたりしてそこから家庭の貧困につながるケースも多い。看過できない問題だ。さらに公立学校教員の1カ月以上の長期療養者数が精神疾患によるもの約9500人、それ以外で8000人。過酷で過労死ラインを超える職場で離職する人もいる。
さて分科会は6つに分かれ、①大学までの教育の無償化②地域格差、家庭格差、障害格差をなくし、教育を多様化する③インプット教育からアウトプット教育へ④経済優先から精神的豊かさへ教育のあり方を変える⑤教員等の勤務環境を改善する⑥個別最適化された全世代型の教育の機会を保障するといったテーマで、それぞれ民間教育関係者100人ほどが毎週または隔週議論を戦わせている。
日本は少子化が進み、第1次ベビーブームの頃の3分の1の出生数になった。その子どもたちが支えなければならない第1次ベビーブームで生まれた高齢者が65歳から75歳を迎えている。労働力が減って企業の廃業が相次いでいる。アメリカや西欧、中国に伍して世界のリーダーとしてあり続けるために今キーは教育だとつくづく思う。GAFAなどの先端企業がもっと育ってほしい。教育の底上げも必要だ。そのためには先行投資としての教育投資がぜひ必要だ。
この文をお読みいただいた方々からもぜひ声を寄せていただきたい。何をどうすればいいのか。世論を盛り上げて日本の国力を伸ばしていかないと衰退し、やがて呑込まれることになる。10年後では遅い。瀕死の病にかかった教育を直す特効薬は何だろうと考えられるのか。諸兄の感想・ご意見をお待ちしている。
(TEL 03・5996・6565)