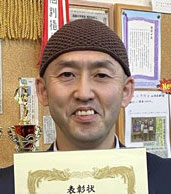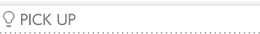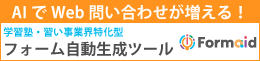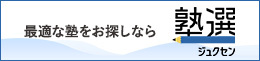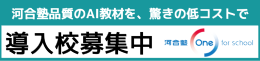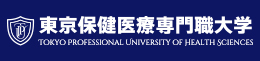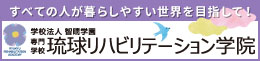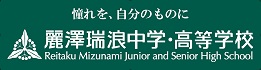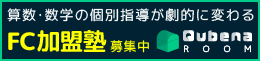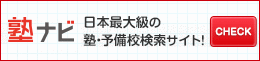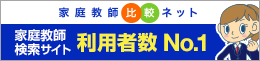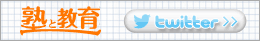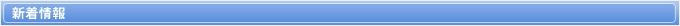
SRJ×好学出版 算数的思考力まるわかりセミナー
なぜ「思考力」が求められているのか?
株式会社SRJ(堀川直人代表取締役、東京都中央区、以下「SRJ」)と株式会社好学出版(長嶋顕信代表取締役、東京都新宿区)は、未来を生き、想像するための「算数的思考力」をテーマにセミナーを2月24日(木)オンラインで開催した。初めて参加される方も多く、SRJの企業紹介に始まり、東京学芸大学数学科教育学分野で活躍中の西村圭一氏による基調講演と二つの塾による事例講演が行われた。
開会に先立ち、株式会社SRJ 取締役 佐伯康雄 営業本部長が開会の挨拶。「弊社は、サービスの提供を通して日本の教育を明るく照らすことをミッションに、社会で活躍できる人づくりに貢献できる最高のコンテンツメーカーを目指しています。本日のテーマ〝思考力〟とは、問題に直面したときに、様々な情報や条件がある中で、いくつもの可能性や筋道を考え、その中から最適なものを選んでいく力だといえましょう。社会で活躍できる人づくりには、こうした思考力、考える力が必要であると考えます。 今回のセミナーが生徒指導、教室運営に少しでもお役に立てれば幸いです」
■基調講演■
未来を生き、創造するための「算数的思考力」
東京学芸大学 数学科教育学分野 西村 圭一 氏
==================================================
東京学芸大学大学院 教育学研究科 西村圭一 教授
東京学芸大学大学院 教育学研究科教授、博士(教育学)iML 国際算数・数学思考力検定研究委員を務めながら、そのほかにも日本数学教育学会業務執行理事・数学教育編集部長など多くの教育現場でご活躍。主な編著書として『中学校新数学科 活用型学習の実践事例集 豊かに生きる力をはぐくむ数学授業』(明治図書 2010年)などがある。
==================================================
思考力とは、そもそもどのようなチカラなのか、思考力とは私たちの暮らしにどのような関わりがあるのか。
算数的思考力のある子は、言われたことをしっかり覚えて、早く正確にやるだけではない。じゃあどうすれば算数的思考力はつくのか。それは小学生低学年のときの体験による。カードに引き算が書いてある。「同じ答えになるものを集めてみましょう、どんな決まりがあるかな? なにか気がつくことはない?」と問う。引かれる数と引く数に同じ数を足しても答えは変わらないことに気づく。初めて見る分数の計算でも、「今までやっていた引き算の決まりを使ってみればいいかな」と考え答えを出す。中学生になり、負の数を学ぶ。「さてどうやる? まず考えてみよう。小学生の頃やっていた引き算の決まりが使えないかな?」小学生のときやっていた引き算の決まりが使えるという思考ができるようになっている。
なぜこういう力が必要なのか。単に計算の答えを求めるならGoogleで出てくる。算数や数学では、〝やっぱり計算、答えを間違わずに求められることが大事〟という価値観が変わりつつある。言われた手順で早く正確にできた方がいいが、それだけで終わるのではなく、学ぶ手前で思考力をしっかりつけておくことが重要。方法を見出す、計算の仕方を見出し、手順化していく。やったものに対して疑問を持ち、他のものも調べてみる。もっといい方法はないか探ってみる。自分で算数を創っていく、これが算数の思考力である。
では、そうしたチカラをどうやって育むのか? 単に言われたことを覚えるだけでは思考力にはならない。長期的に考え思い出し、〝ああそうか!〟と、腹打ちする体験をさせていくことである。思考は覚えるということではなく、感動とともにつなげていくことなのだ。〝そうなんだー〟で終わらせず、面白さを共有していくことが大事である。
そのためにしなければいけないのは、大人のUnlearn(アンラーン)。アンラーンとは、これまでに学んだ知識や身に付けた技術を振り返り、さらなる学びや成長につながる形に整理し直すプロセスだ。算数を教えるとき、算数が得意だった先生や保護者は、自分の成功体験で教えるため、子どもたちは、先生や保護者の価値観の範囲内での思考力しか付かない。
最初にやり方を教えるのではなく、子どもに新規の場面に遭遇させ、そこで持ってる知識や技能を柔軟に組み替え、新しいものを創り出していけるよう、日々思い巡らせ実践していただけたらと思う。
■事例講演■
「速読、思考力トレーニングの活用について」
個別指導Q 笠木 誠 代表
「わかる・できる・面白い」をモットーに 2010年、函館で開校。現在生徒数は210名。2015年に速読の全国大会で日本一となり、以降7回日本一を獲得している。
2013年に速読、思考力トレーニングを導入。速読により右脳をトレーニング(直感力・判断力・記憶力アップ)し、思考力によって左脳をトレーニング(思考力・論理力・推論力アップ)している。
小1~小3は、『スーパーキッズコース』と銘打ち、速読40分+音読・思考力40分で週2コマとしている。このうち思考力が25分、音読15分。小1~中学生まで思考力40分をまるまる行うコースもある。テキストは算数アドベンチャーと算数ラボの両方を使用。考えることやいろいろな考え方にトライすることを重視している。
思考力トレーニングは考え方を学ぶということ。頭の中で考えるだけでなく、手を動かすことが重要。与えられている条件から、わかっていることを書き込むのだ。今わかること、できることをやっていくと、その先に何をすればいいのか、ひらめきが生まれる。
速読+思考力+音読の組み合わせは相性がよく、保護者の満足度も高い。「なんとなくのわかった」ではなく、「本当のわかった」はワクワクするほど面白い。「じっくり考える」経験を習慣にしたい。
■事例講演■
「算数ラボ、思考力検定の活用について」
株式会社やる気スイッチグループ チャイルド・アイズ事業本部
執行役員 鈴木愛子 本部長
チャイルドアイズは、「やる気スイッチグループ」の幼児、小学生部門、思考力育成部門として2001年に誕生。長年のノウハウを生かし、子どもたちの才能や可能性を見つけ、将来の成長に向けた大きな力となる思考力を育んでいる。
2021年12月末現在、全国で134教室。脳科学をベースにしたメソッドによりカリキュラムを編成。幼児コースでは具体物を操作し、小学生になるとプリントによって知識・経験をインプット(理解する、認知する、記憶する)し、考える力(発想の転換、推理する、想像する)を育み、言葉や行動によって考えをアウトプット(表現する、伝達する)できるよう知的好奇心を刺激する。
思考力検定は年3回実施、年間1000人程度が受験している。小学校低学年向け「思考力アドバンス」コースの日々の学びの成果の見える化や、何割の正答率で合格したのかを振り返り、同じ級を何度も受験することで定着と自信を培う。
思考力検定では、銅、銀、金メダル合格基準があるので励みになる。検定前には、1カ月前を目安に直前講座として算数ラボを活用。自分で目標を立て、そこに向かって目に見えない階段を上っていくことで、充実感、達成感、自信などを身に付ける。今後は、小学校コースで算数ラボも取り入れている思考力メソッドをご紹介できるようにしたい。
最後に、好学出版より今春4月に発刊される『算数ラボ2』の案内とSRJからは思考力のトレーニング可能な算数ラボ搭載の『TERRACE』などを紹介。思考力検定や算数ラボで楽しみながら、考えることに日々取り組んでいただきたいと述べ、会を締めくくった。