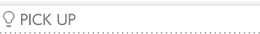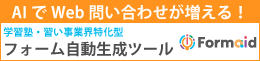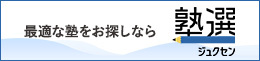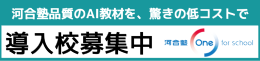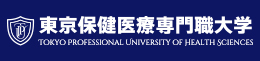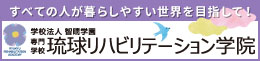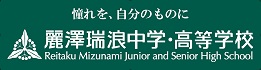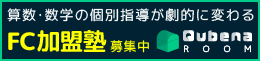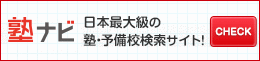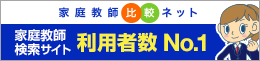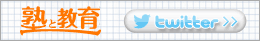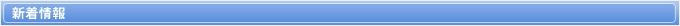
SRJ「秋期運営勉強会」 一強十弱時代、競合から協同へ
複数教場運営塾の現場管理・運営手法を共有
株式会社SRJ(代表取締役社長 柏木 理氏 東京都中央区)は、東京・大阪にて「2024秋期運営勉強会」を開催した。
大手学習塾の業績は伸びている一方、上半期の学習塾倒産数は過去最多。地方の個人塾や教室数の少ない塾は厳しい状況で、淘汰が激化しているのが業界全体の縮図だ。競合から協業が当たり前に起きている時代、1社で乗り越えていくよりも協力しながら取り組む環境下にある。
勉強会には学習塾の垣根を越えて関係者が集結し、「速読解力講座」「速読聴英語講座」の運営や集客の手法について共有し合う有意義な場となった。各社のプロジェクトチームの取り組みや速読事業成功の秘訣について、3講演の内容をリポートする。
[東京会場講演]
株式会社茨進 速読受講促進チーム
チームリーダー 齊藤 綾乃 氏
同チームメンバー 小森 宏美 氏
PJチームによる速読運営 各部門目線で併用を促進
2025年に創業50周年を迎える株式会社茨進は市進グループに属し、茨城県内に46校舎を構える。中学受験や個別指導、茨進ハイスクール、ウイングキッズ・ラボの各コースに併用するオプションとして、小1生から高3生を対象に「速読解力講座(以下、速読)・速読聴英語講座(以下、速読英語)」を展開している。
茨進では2013年に速読、2015年に速読英語の導入をスタートした。現在は38教室で速読の受講生数は約500名、速読英語は約300名に拡大中だ。いばしん個別指導学院つくば天久保教室・つくば大穂教室の教室責任者を務める齊藤氏は、プロジェクトチームが発足した背景について次のように話した。
「プロジェクトチームの目的は集客・併用促進、コース設計・イベント企画、運営ツールの作成です。今年度は入社4年目から18年目までの幅広い年齢の5名で構成され、各部門目線でコース併用促進ができるように、本部と各教室の間の架け橋を担っています。
小学生から高校生までの個別指導部門に速読と速読英語を集約し、1人ひとりに確実に受講してもらうために作成しているのがトレーニングメニューです。作成にあたってはSRJが提供する素材サイトを活用し、テンプレートを活用すれば毎月の作業は5分ほどです」
速読・速読英語は、各メイン講座の受講生たちにいかに併用を促すかがポイントとなる。多くの生徒は集団指導や個別指導など基幹部門のコースに、追加で速読や速読英語を受講するケースが多い。そのため、授業前後の受講希望時間帯を事前に聞き取り、時間割を設定することで受講管理・欠席管理もしやすくなるという。
小森氏はウイングキッズ・ラボ守谷駅前教室で、算数パズル教室やロボット科学教室を担当している。
「各教室によってブースで区切られたスペースや自習スペース、映像受講スペースに速読用タブレットを設置しています。壁面にスピードマスターズの得点で競い合う掲示物を貼り出すことによって、体験授業を受講した保護者の反応も上々です」
保護者向け募集ツールで読書速度を比較・数値化
プロジェクトチームは進学校に通う高校生と筑波大の非常勤講師を対象(340名)に、読書速度計測とアンケート実施した。
「併用の提案をする際、保護者から『どういう目標で取り組めばよいのか』、受講生には『志望校にはどれくらいの速度が必要か』と問われ、学校ごとに落とし込んだ内容を説明できていないという課題が背景にありました。
そこで読書速度計測を行いました。茨城県内でトップ公立高校とされる土浦一高・水戸一高・竹園高に通う生徒たちや県立中高一貫校である並木中等や日立一高附属中に通う生徒たち、さらには筑波大学に通う講師たちの協力を得てそれぞれの平均速度を計測し、それを一般的な中学生の平均速度と比較したところ、相当な差が明らかになりました」(齊藤氏)
難関校に通う生徒たちの読書速度を数値化することによって、より茨城県特有の内容に特化し、保護者向けリーフレットの説得力が増したという。
同様に、速読英語では読書速度の計測結果として、一般の中学生の平均と〝難関校の先輩〟とでは計測結果に3倍の差が開いた。これを保護者に示し、併用促進や併用を外すことを抑止するという意味でも、数値化は非常に有効だと齊藤氏は強調する。
「また、中3生対象の入試説明会において、速読英語に絞った体験チケット付きのチラシを配布しました。各科目の入試傾向や対策を説明する中で、速読英語なら読解もリスニングも両方トレーニングできると訴える手法です。入試内容の説明を聞いた直後に、その場で受講や無料体験希望のアンケートに記入してもらい、現コースとの併用につなげています」(齊藤氏)
さらに、速読もしくは速読英語を6か月以上受講中の生徒を対象に調査し、「成績アップリスト」を作成した。受講前後の成績の変化を手作業で拾い上げ、83%が成績アップしていることが判明した。伸び幅の大きい事例を保護者向けリーフレットに掲載し、「8割以上の成績が上がっている」「偏差値が20近く上がった生徒もいる」と明示している。
その他、「速読・速読英語無料招待キャンペーン」などのイベント企画も現在進行形だ。
齊藤氏はプロジェクトの課題と目標について、次のように力強く締めくくった。
「各教室からの意見の吸い上げを強化し、フィードバックする流れを構築して運営に関わらない社員への働きかけも注力していきます。受講者数1000名に向けて、受験終了学年の継続受講率に貢献していきたいと考えています」
[大阪会場]
第1部講演 :
株式会社学習受験社GAZ(ガゼット)
運営戦略本部 取締役副社長 吉田 知生 氏
第2部講演:
株式会社チアリー
大阪事業推進部 速読プロジェクトチーム チームリーダー
福島 誠一郎 氏
経営難を乗り越えた変革
ブランディング戦略とは?
株式会社学習受験社ガゼットは沖縄エリアで中学受験、福岡エリアで小学校受験を対象とする幼児教育の学習塾を展開している。現在は、福岡県内で1拠点・生徒数350名の規模を誇る。しかし、生徒数の減少や合格実績の低下で経営難の時期があったと吉田氏は明かした。
「顧客中心の経営視点が弱く、変わらないテキストやカリキュラム、属人的運営、数値資料を活用しない、やりたい指導をする状況でブランディングが定まらない状態に陥っていました。2016年度は4拠点で生徒数279名でしたが、2020年度には190名まで落ち込みました」
では、どのように変革を遂げたのだろうか。
「まず4拠点から1拠点に絞る集中戦略、メンバーによる『オリジナル合格メソッド』の再考、教室のリニューアルなどを行いました。
また、合格実績は福岡教育大附属小福岡校に集中し、合格者数20年連続ナンバーワンを死守することに全力を投じました。西南学院小学校も14年連続ナンバーワン、2年連続占有率90%以上を達成し、寡占化するべく取り組んできました」
こうして合格シェアやブランド強化を拡大する中で、業績は回復へと向かった。「ブランドは意識的に創出するテーマ」だと吉田氏は強調する。
「ブランディングの定義は顧客に対して独自価値を創造することです。意識的に創造していかない限り、ブランディングは生まれません。生徒数が衰退した時期はポジショニングマップにおいて横軸に価格、縦軸を合格実績とすると、月2万8000円~3万3000円の真ん中ぐらいで、埋もれてしまう状況だと認識しました。
そこで考え方を変えて、縦軸を希少性、横軸を模倣困難性としました。まず他塾のポジションを位置づけて、ガゼットを一番右上、つまり“模倣が困難で希少性が高い塾”にポジションを置くことでブランド化ができると考えました」
希少性、模倣困難性を意識的に創出する積み重ねこそが重要な要素となったのだ。
「笑顔・専門性・独自性が社員に求めるスキルだと明確に定め、人材育成や研修に取り組んできました。専門性は〝福岡エリアの名門小学校受験のオリジナル要素が強い〟こと、独自性は〝ガゼットしかできない、伝えられない、発信できないこと〟と設定しました」
しかしながら社員たちは「自分は独自性高い」という思い込みに陥っていたと吉田氏は指摘する。
「ブランド創出の2大障壁といえる、〝現状維持バイアス〟と〝確証バイアス〟を克服しなければなりませんでした。データ基軸運営で数値化・標準化し、半年に1度の〝保護者アンケート重視運営〟に舵を切り、重点改善事項として変化や検討を先送りできないしくみを作りました」
ガゼットはチラシを一切使わず、ブランドアップを目的に記事形式や対談形式でフリーマガジンや地域情報誌を発刊している。またYouTube「ガゼットチャンネル」の他、Instagramの発信頻度を上げて単純接触効果を増やしたことが、顧客のファン化に非常に有効だと吉田氏は明かした。
「企画書作成兼会議への出席を広告業者に外部委託しています。月10万円ほどかかりますが、社内からは出てこないアイディアやさまざまな広がりなどのメリットを実感しています」
幅広い世代が受講する速読事業成功の秘訣
株式会社チアリーはショッピングモールや百貨店、スーパーを中心に映像学習のパソコン教室を展開し、全国に88直営教室を構える。そのうち、65教室で速読講座を設けている。
「2018年に速読講座を導入する際、社会人も含めた全世代をターゲットに据えました。現在、会員数1115名で退会率は3.1%です。退会者の平均継続月数は18.3か月で、中学生以下が17.7か月、高校生以上が18.7か月です。中学生以下が占める割合は速読受講生全体の25%程度で、全世代の方に受講いただいています」(福島氏)
福島氏は速読事業成功の秘訣について、本部体制の構築を挙げた。各部門から選抜された6名の実行部隊で速読プロジェクトチームを組織化し、社長自らもメンバーに加わっている。
「速読講座の運営支援として会員数や利用回数、退会数、退会率、継続数、売上、利益の計数値の集計や、SRJ・本部・教室間における情報の共有を行います。その他、販売促進キャンペーンや教室対抗戦、速読交流会の企画・運営も担っています」
本部と教室が一体となった継続強化の取り組みが、チアリーの強みだ。
「速読プロジェクトチームが主催する社内の速読交流会は、最大の研修勉強会として教室長を対象に3か月に1度開催し、SRJ担当者にも参加いただいています。事前のアンケートでテーマを伝え、それに関する質問や意見を集めて取り上げてほしいテーマを聞き取ります。質問や成功事例、失敗事例を募ることによって、自分だけが悩んでいるのではないことが教室長たちに伝わり、セールストークなどを教師間で共有できるメリットがあります」
速読交流会のテーマは、「検定のフィードバックの方法を知りたい」という意見が多かったという。「交流会に参加するたびに、こんなに受講生に楽しんでいただけるコンテンツだったのだと思い出すことができ、モチベーションが上がります」「他教室での取り組みを聞けることは刺激になります。確実にプラスの効果だと感じます」といった意見が寄せられた。
また、継続強化の取り組みとして、チアリー独自の〝速読スピードマスターズ教室対抗戦〟も特徴的だ。半年に1度、5月と11月に開催され、同じタイミングでインストラクターの対抗戦も開催している。
「速読を導入したメリットは、パソコン教室全体の継続率アップです。速読の売り上げが毎年約5000万円規模になり、経営の安定化にも貢献しています」










![[左] (株)茨進 速読受講促進チーム チームリーダー 齊藤綾乃氏 [右] (株)茨進 速読受講促進チーム チームメンバー 小森宏美氏](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2025/01/2025_01_p58_sokushin.jpg)