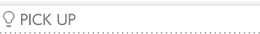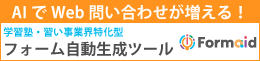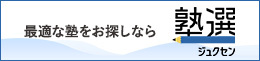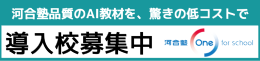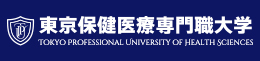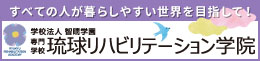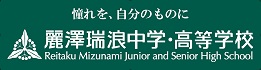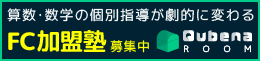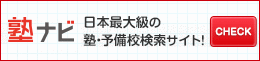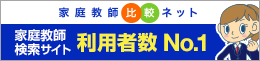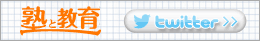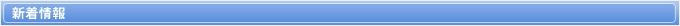
STUDYPLUS AGENDA 2024AW
人口減少とこれからの教育業界。
課題を見据え、共に考える。
2024年6月、スタディプラス株式会社(廣瀬高志代表取締役社長、東京都千代田区)が開催した、第1回スタディプラスアジェンダに大きな反響が寄せられる中、同年11月第2回スタディプラスアジェンダが開催された。5つのセッションを通して、少子化や労働人口の減少を背景に、コロナ禍の中で加速した不登校の増加をはじめインターネットやSNSの普及で鮮明化してきた個性やアイデンティティの多様化などをテーマに様々な事例や情報などを共有した。今回は、3月号の続きでセッション3からダイジェストで紹介する。
いま考えるべき教育と経営の論点 第2回 スタディプラス アジェンダ
[Session 3]
ポストAI時代、教育機関に求められる変化とは
スピーカーは、デジタルハリウッド大学教授・学長補佐、一般社団法人 教育イノベーション協議会 代表理事、株式会社グローナビ代表取締役の佐藤昌宏氏。聞き手はスタディプラス株式会社 取締役の宮坂直氏。
宮坂 この数年で生成AIが急速に普及し、教育の分野においても活用されるようになりました。子どもたちが学びの中でAIを活用するにあたり、教育機関に求められることは何なのか。デジタルハリウッド大学学長補佐・教授の佐藤昌宏氏に登壇いただき、EdTechの研究や実践に取り組む立場から、これからのICT教育の在り方についてお話しいただきます。佐藤氏は、日本初の株式会社立大学院の設置メンバーの一人として学校設立を経験。内閣官房教育再生実行会議技術革新ワーキンググループ委員、経産省未来の教室とEdTech研究会座長代理など教育改革に関する国の委員や起業家へのアドバイザーなどを歴任されています。
AIがもたらす教育環境の変化
佐藤 テクノロジーは必ずや人類を幸せにする必要不可欠な道具だと確信しています。そしてテクノロジーの進化は社会に大きなイノベーションをもたらしますが、時には破壊的であったり、これまでの価値観や常識を根底からひっくり返すこともある。だから上手に使い学び続けることが必要なのです。EdTechとは、デジタルテクノロジーを活用した教育のイノベーションのことであり、先端技術のみならず汎用技術を活用して教育のビフォーアフターを創出することです。EdTechで目指す世界観は、いつでもどこでも誰でも質の高い教育が享受できる世界の構築。あらゆる教育現場において、現代の知恵であるデジタルテクノロジーを人類の幸せのために使えるリテラシーを備えていることが重要です。
ポストAI時代に子どもたちに求められること
佐藤 技術の進化が止まらない中、人間中心の教育に必要な能力は(1)技術の可能性と限界を知ること、(2)AIを制御する力、の二つです。前者はよく言われる情報活用能力です。例えば、インターネットのIPアドレスは足跡(変なサイトに行くとバレる)、エコーチェンバー現象(SNSなどで類似の意見ばかりに触れると正しいと思い込む)、内容ベースフィルタリング(フィルターバブル)や協調フィルタリング(レコメンドの仕組み)などを知らないと、過度に技術を恐れたり、人や社会を傷つけてしまいますから、教育でテクノロジーを使い、教育でデジタルリテラシーを学ぶ必要性があります。
AIを制御する力には基礎学力とリベラルアーツが重要です。漢字予測変換利用時に正しい漢字を選ぶことができるか、英語の自動翻訳利用時に間違いや違和感に気づけるか、スピーキングAI活用時に正しい発音を理解しているか、Chat型AI活用時に要約内容を確認できるか、文章や音楽、絵などの自動生成時に感動する創作物を創れるかなど。テクノロジーが出した答えに対して正しく対応できないとテクノロジーを制御することはできません。自身の価値観、判断基準ともいえる倫理・道徳・哲学・真善美を見極めるリベラルアーツ、教育の必要性はここにあるのです。
ポストAI時代に教育機関に求められること
佐藤 EdTechが進むと何が起こるのかというと、学習者中心の学びになり、教育という仕組みを越える学びが手に入るようになります。今やるべきことや変わることに備え、必要なステップを踏み、学習者の自由な利活用を制限しない基盤的な運用が求められています。BeyondGIGA、いつでもどこでも誰でも恩恵を受け、効果を得て豊かになる社会。今は変革期(過渡期)です。国だけでなく民間も一緒に声をあげることで、子どもたちのためのより良い環境を作ることができると思います。
[Session 4]
多様化する教室経営の新戦略
スピーカーは、株式会社メイツ 代表取締役CEOの遠藤尚範氏と、株式会社すららネット 代表取締役社長の湯野川孝彦氏。
宮坂 近年、テクノロジーの進化に伴い、子どもたちの学びの手段は多種多様になり、学ぶ場所や学び方の選択肢はこれまで以上に広がってきています。このセッションでは、これからの学習塾の在り方や従来の学習塾にとらわれない学びの場の可能性について遠藤様と湯野川様に登壇いただきます。遠藤様は、学習塾専用ICT教材『aim@』を使用する「進学塾メイツ」および中高一貫校専門「個別指導塾WAYS」を運営。関東・関西に34教室を展開中です。湯野川様はアダプティブな対話式レクチャーとドリル・テストが一つでできるオールインワン教材『すらら』を開発。現在約1200の塾、約1400の学校で活用中です。
少子化に対する取り組みや戦略
遠藤 少子化への対応策は、LVT(Life time value)の中でも単価を上げる戦略ではなく、長く通っていただくLife timeの点に力を入れてきました。声かけなどを細分化して取り組む中で、カスタマージャニーマップを作成し管理。入塾の契約後、将来の夢を実現するまでの流れをマップ式で可視化し、最適なタイミングで最適なアプローチにつなげるものです。
湯野川 全2500校のお客様の半分は塾、半分が学校。少子化が進むため今までとは違う集客について話していきます。お勧めしたい戦略の一つは34万人に増えた不登校対象のフリースクール。「すらら」を使って出席扱いの認定も得られ、差別化につながる。自治体にもよりますが,補助金が出ますし商圏を飛躍的に広げることができるのです。
労働人口の減少にどう対処するか
宮坂 日本全体で人手が644万人不足し、教育業界では28万人が不足する2030年問題。事例やお考えをお聞かせください。
遠藤 塾の開校時、「早稲田に行く塾」というニッチ戦略は失敗。次に駅近で早稲田生が1時間500円で教える塾として60名ほど集客でき、いろいろなニーズが見えました。当時、全教科教えられる私一人で小学生から中1~高2まで20~30名をみていました。そのとき、経験のない先生でも1対多人数を教えられるサービスがあればという思いが、現在の弊社サービスの原型となりました。当時の考えでできたサービスが現状の先生不足への対応策にもなっており、たくさんの引き合いをいただいています。教室では、ホワイトボードをパーテーション代わりに置き、長机を用いて12人ひとまとまりを一人の先生が教えます。ルールを定めておけば、先生不足には1対多人数がいいと思います。
湯野川 弊社では、以前からかなり振り切った個別指導塾を実践しています。個別指導塾ですが生徒は「すらら」だけで学び、教室長一人、アルバイト講師ゼロという状態で一度に20名くらいみることができます。90分授業のうち45分はEdTechを使い、残りの45分をアルバイト講師が教えることで人件費は半分に。また、大手塾が理社で困っているとよく聞きますが、指導をEdTechでやり、先生が校舎を回ってケアすれば先生を減らせます。採用では、これまで採用してこなかったような教務経験ゼロでも生徒のケアが得意な方に着目しています。
今後の戦略と教育の在り方
遠藤 ICTにおいて、学習塾では啓発期に突入。良い事例がたくさん出てきています。弊社も胸を張って啓発していきますし、導入しているお客様、導入していないお客様も含めて事例発信がこれから増えていく。「ここが大事なポイントとしてうまくいった」という地に足ついた議論ができると思います。
湯野川 今後の学習塾業界の戦略と在り方で申し上げますと、公教育との連携が挙げられます。塾と学校、保護者が学習者のデータを共有して皆で成長を見守るというのが理想の姿。次世代で実現すればと思います。あとは海外進出です。スリランカ、インドネシア、エジプト、カンボジアなどに行きますと大変伸びしろがあるので楽しくてたまりません。日本の教材はよくできているので勝機はあると思います。
[Session 5]
学びの多様化、学習意欲を高めるために
スピーカーは、ベネッセ高等学院学院長の上木原孝伸氏と、クラスジャパン小中学園 校長の小幡和輝氏。
宮坂 2023年、不登校児童生徒数が34万人となり、中学生は約15人に1人が不登校傾向。2030年には10%が不登校になると言われています。一方2000年以降、通信制高校の数と生徒数は増加し続けています。入試の多様化や学びの場の多様化が進み、求められる学力や学びそのものの定義も変容のときを迎えています。このセッションでは、上木原様と小幡様に登壇いただき、学習意欲の引き出し方や主体性の育み方など、具体的な取り組みについてお話しいただきます。
子どもの学びの環境
上木原 教育機会確保法が大きかったと思います。文科省が不登校は問題行動ではありませんということを明確に示した。法律に基づき、フリースクールで、出席の認定が受けられるようになってきています。また、教育の機会が確保されていないことが問題なのであって、教育機会を確保するためにフリースクールやICT教材などを紹介していきましょうということになっています。学校に来させることがゴールなのではなく、その子の学びを止めないことがゴール。不登校は増えても、学びの方法を見つけている子が増えています。
小幡 僕は8歳のときに学校に行かない選択をしました。クラスジャパン、オンラインのフリースクールや著書などを通して、「不登校は不幸ではない。学校に行かなくてもいいよ」という考え方を発信し始めたのが2017年。不登校になれなかった子が、堂々と不登校になれる時代に来ていますが、学びの環境や機会はまだまだ足りません。
多様な学びの場づくりとその重要性
上木原 90年代から2000年代くらいまでは、中学・高校・大学と偏差値のレールに乗っていけば幸せになっていく子が多かったという実感があります。2010年くらいから多様性の時代となり、この子はもっと違う角度から光を当てたほうが幸せになれるんじゃないかとかいうことが認められる社会になってきました。N高はネットの学校なので不登校もなければ障害もない。環境要因で障害はなくなるということを体現している学校です。教育に正しいや絶対はありませんが、唯一正しいことがあるとするならば、その子が学べる選択肢がたくさんあることです。通信制を選択肢の一つとして普及させていくことが、子どもたちの未来をつくるために重要だと感じています。
小幡 クラスジャパンは2018年に開校したオンラインのフリースクールです。生徒一人ひとりに担任が伴走し勉強をサポート。eスポーツやイラスト、プログラミングなど得意を伸ばす部活動もある不登校生徒の新しい居場所です。生徒が作ったプログラミングがテレビで紹介されたり、自由研究のコンクールで審査員特別賞を受賞するなど、嬉しいことが続いています。ゲムトレは2019年に創業。eスポーツやゲームをオンラインで学べるものです。日本中で友だちができたり、自己肯定感アップにつながっています。
学習意欲を引き出し、主体的な学びを育むには
上木原 私たちがポリシーとして大事にしていることは、子どもたちの自己決定です。そのために、生徒を信じること、本音を引き出すこと、待つことという、3つの信念をもって生徒と向き合っています。
小幡 ゲームはいろいろな用途があります。直接説明せずに、その人が面白いと思うところまでやらせる、これはまさに教育です。子どもたちが今何をやっているか、何に興味があるのかはキャッチアップすべきです。今の教育は、教材が山ほどあり、モチベーションさえあれば好きに勉強できる時代。先生の役割はモチベーションをどう高めてあげられるかが大事です。
Youtube はこちらから
https://www.youtube.com/@StudyplusAgenda










![[左] スタディプラス(株) 取締役 宮坂直 氏 [右] デジタルハリウッド大学 教授・学長補佐 佐藤昌宏 氏](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2025/04/2025_04_p28_sessiion3.jpg)
![[左] スタディプラス(株) 取締役 宮坂直 氏 [中] (株)メイツ 代表取締役CEO 遠藤尚範 氏 [右] (株)すららネット 代表取締役社長 湯野川孝彦 氏](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2025/04/2025_04_p29_session4.jpg)
![[左] スタディプラス(株) 取締役 宮坂直 氏 [中] ベネッセ高等学院 学院長 上木原孝伸 氏 [右] クラスジャパン小中学園 校長 小幡和輝 氏](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2025/04/2025_04_p30_session5.jpg)