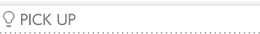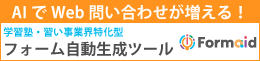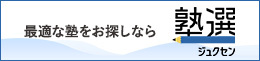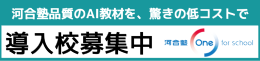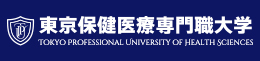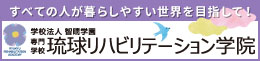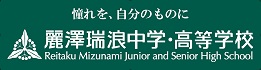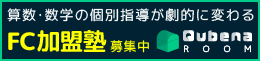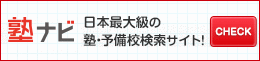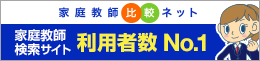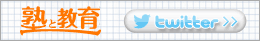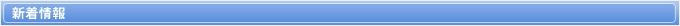
民間教育をめぐる国政での動きを大島九州男氏が述べる
サービス業から教育産業へ
平成22年10月21日、参議院文教科学委員会で高木文部科学大臣(当時)が私の質問に対して「文部科学省が関係する団体に学習塾は当然含まれる」と答弁したのが始まりだった。
学習塾は経済産業省が「サービス業」として所管していたが、この歴史的答弁がきっかけとなり、文部科学省が民間教育機関として捉えるようになる。その後、学習塾のノウハウが公教育の場に浸透していったことは記憶に新しい。
省庁間の連携
経産省が主導するSociety5.0時代の「未来の教室」実証事業では、EdTech・個別最適化・文理融合(STEAM)・社会課題解決をキーワードに新しい学びの社会システムが提唱され、経済産業省、文部科学省、総務省が連携して推進している。教材にはeフォレスタ、Qubenaなど学習塾のノウハウが採用され、まさに省庁間の連携に学習塾が含まれている好例だ。
教育費の負担を目指し
この流れを加速させるために必要な改革は教育費の負担減だ。世界を見渡せば、フランスでは個別指導や家庭教師への支出が所得税控除され、韓国では学習塾や体育施設での受講料が税額控除される。米国にも様々な税制があるが、ミネソタ州では個別指導や音楽レッスンの受講料が所得税控除となる。
平成25年税制改正で教育資金贈与信託を実現できたが、前述した教育にかかる税制改正は道半ばだ。
いよいよ参院選
いまや1兆円産業へと成長した学習塾は、我が国の教育水準を日々向上させ、さらには雇用の受け皿としての社会的役割も計り知れない。参院選で私は「民間教育費控除」の創設を提唱したい。医療費控除、生命保険料控除と同じ仕組みだ。
省庁間連携と学習塾が両輪となり、教育を支える「オールジャパン」として邁進できる制度の構築を目指していきたい。
(大島九州男 記)