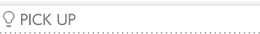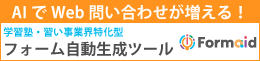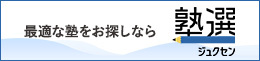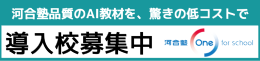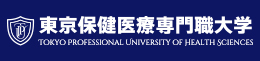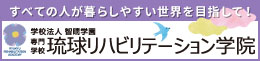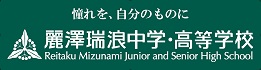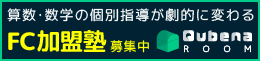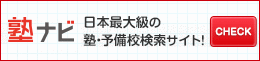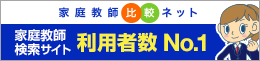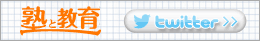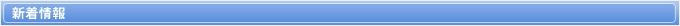
(公社)全国学習塾協会「特別セミナー」を開催!
6月9日(日)、東京・市ヶ谷にて公益社団法人全国学習塾協会の理事会・総会が行われ、安藤大作氏が全員一致で会長に再任された。その後、「特別セミナー」が開催され、経済産業省教育産業室の柴田寛文氏が教育産業振興の取り組みについて講演を行い、経済産業省「未来の教室」とEdTech研究会の委員を務める安藤氏が、研究会の報告を行った。
4期目を迎えた安藤会長、「新たな気持ちでリスタート」
特別セミナーに先立ち、総会・理事会で全国学習塾協会会長に再任され、4期7年目を迎えた安藤大作氏は、本誌の取材に対して次のようにコメントした。
「4期目を迎えるにあたり、新たな気持ちでリスタートする所存です。今、日本の教育は大きく変わる節目を迎えており、当協会も〝これまで通り”を積み重ねるだけでは不十分です。これからは子どもたちを取り巻く仕組みや環境そのものを変えていく必要があり、特に重要になるのが、公教育と民間教育とのシームレスな融合だと考えます。放課後に学校の学びを〝補う”存在にとどまらず、学校に入り込んで、学校と一緒になって、子どもたちの学びを支えていく。そんな存在としての民間教育を推進していきたいと考えています。
また、4期目には、全国学習塾協会への加入率50%を目指しています。昨年4月には『民間教育推進のための自民党国会議員連盟』が発足し、10月には議連総会の場で7つの要望を提出しました。こうして国の新しい教育施策に対して、民間教育の立場で堂々と話し合い、提言していく。新しい10年は自分たち民間教育事業者が創っていくのだという気概で団結して臨むためにも、ぜひ、当協会に加入していただきたいと思います。さらに、任期中には、発信強化、政策提言、コンプライアンス強化、民間教育団体連絡協議会の活動推進、寄付のスキームの確立などに取り組み、民間教育のプレゼンスをさらに高めていきたいと考えております」
学習塾の経営力向上に役立つ2つの制度を紹介
続く特別セミナーでは、経済産業省商務・サービスグループサービス政策課 課長補佐、教育産業室 室長補佐の柴田寛文氏が、「経済産業省における教育産業振興の取組について」と題した講演を行った。
柴田氏は、産業金融政策、ヘルスケア政策、東日本大震災後のエネルギー政策の見直しなどに関与したのち、2018年7月より現職。自身の出自や中学受験に向けて通った塾での思い出、2児の父親としてのエピソードなどを交えて自己紹介をしたのち、本題へ入った。
1つ目のテーマは、学習塾業に係る経営力向上に関する指針について。事業所管大臣が策定する事業分野別指針に基づき、「経営力向上計画」を立案・申請し、認定された事業者は、様々な支援や優遇を受けられるという「中小企業等経営強化法」のスキームを紹介。
学習支援業にあたる学習塾(各種学校でないもの)が経営力向上計画を策定するうえで必要な要件などを解説した。
柴田氏は「経営力向上計画の策定プロセスを通して、これまでの事業や業務を見直すことが重要」とし、「これから教育分野で政策を立案していく際に、学習塾事業者の皆様には重要なプレーヤーとして存在してもらう必要があると考えている。この度の事業分野別指針を参考にしていただきながら、さらにバージョンアップされることを期待します」と述べた。
2つ目のテーマは、「IT導入補助金2019」について。IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者が生産性向上に役立つITツールを購入する際に、その費用の一部を国が補助する制度。「申請資格の有無や必要な要件を確認する」、「補助金が交付されるITツールについて理解する」、「導入したいITツールとIT導入支援事業者を探す」、「補助金申請の手続きを確認する」という4つのステップについて解説した。最後に柴田氏は、「自塾にはどういう課題があり、その解決のためにはどういうツールが必要なのかを明確にしたうえで、ぜひ補助金制度を活用していただきたい」と述べ、講演を締めくくった。
「未来の教室」とEdTech研究会
第2次提言のキーワードは、「STEAM」と「個別最適化」
続いて、「未来の教室」とEdTech研究会の第2次提言に向けた論点について、同研究会委員を務める安藤大作氏が報告を行った。キーワードとなったのが、近年、見聞きすることの増えた、「STEAM」と「個別最適化」だ。
STEAM(Science, Technology,Engineering, Art, Mathematics)について、安藤氏は、「STEAM=理数教育、と考えがちだが、各教科での学習を実社会の課題解決に生かしていくための教科横断的な教育というのが本質。
今後の提言では、リベラルアーツ(教養)としてのArtの位置付けを強調し、STEAM教育とは何か、STEAM教育で何を目指すかを明らかにしていきたい」と述べた。また、「午前=EdTechを用いた個別学習、午後=STEAMの協働学習」という同研究会が描く「未来の教室」のカリキュラム・マネジメントのイメージも提示した。
さらに、基本的な知識・技能を習得するために有効かつ必要なのが、ICTを活用した「学びの個別最適化」であるとし、従来の画一・一斉型の授業ではなく一人ひとりに応じた課題に取り組む新しい授業のあり方を提示した。一方、「個別最適化については、ICTに対する誤解・偏見をはじめネガティブな意見もある。教育現場には不安や疑念があって当然だと思うので、慎重に進めていきたい」と述べた。
また、学校のICT環境の整備など、学びの最先端であるEdTechを学校教育において有効に活用するための課題も挙げ、「今後も研究会での議論の内容を協会員の方々と共有していきたい」と締めくくった。
講演に続いて質疑応答が行われ、会場からは柴田氏から説明のあった制度についての質問などが挙がった。なお、全国学習塾協会は、「学習業に係る経営力向上に関する指針」および「IT導入補助金2019」に関する説明会を開催するなど、今後も経済産業省と連携して学習塾に有益な情報を発信していく予定だ。
※なお、「未来の教室」とEdTech研究会第2次提言は6月25日に公表されました。