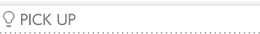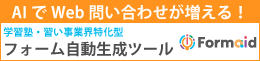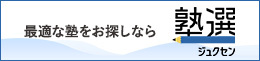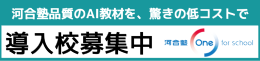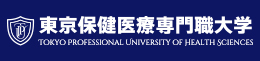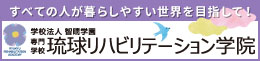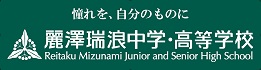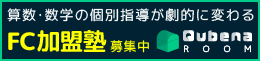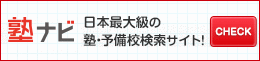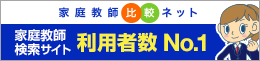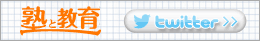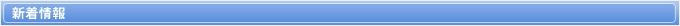
教育資源としての民間教育 第20回
公益社団法人 全国学習塾協会 安藤 大作 会長
子どもたちを取り巻く社会課題に対して大人が立場を越えて向き合うべき
9月の最初は児童生徒の自殺が最も多いと聞きます。
また14万人ともいわれる不登校ですが、不登校気味なども合わせると実に44 万人にものぼると言います。
学校に居場所がなかったり、相談する相手がいなかったり、自分の存在価値などに悩む様々な子どもたちに塾は寄り添ってきました。学力面での心配の払拭のみならず子どもたちの居場所としても存在してきました。
文部科学省は、「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用して行った学習活動について、校長は指導要録上出席扱いとすることができる」としています。しかし現実に出席扱いとなっている児童生徒数は149人(平成29年度)しかいません。実に0.01%です。いまだ不登校のまま欠席扱いになっていたり、内申書の記載を含めて、学習の遅れのみならず進路選択の妨げになったりしているのが現状です。文部科学省は出席扱いの一律基準を示しておらず、学校の評価(校長の評価)に依っているのが現状です。
当事者もその周辺の大人もこのルールを熟知していないがために積極的活用に至ってないものと思われます。
また違和感を感じざるを得ない部分として、「自宅において」と場所を自宅に限定しているところです。例えば塾ではいけないのでしょうか?
また「IT等を活用…」ということですが、対面指導ではいけないのでしょうか? これに関しては、対面指導を行うものとして「在籍校の教員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの専門家のほか、教育支援センターの職員、教育委員会等による事前の指導・研修を受けたボランティアスタッフなどを想定している」とありますが、なぜそこに塾などの民間教育事業者が記載されないのでしょうか?
今、子どもたちはあちこちで悲鳴を上げています。子どもたちを取り巻く社会課題に対して、大人が立場を越えて向き合うべき時を迎えているように思います。子どもたちの幸せを思い教育活動に身を置く多くの関係者が力を合わせるべき時に、そのプラットフォームを作っていくことが未来への足掛かりになると思っています。これまでの価値観やスキームを大きく一度見直すべきではないかというメッセージが、昨今の多くの問題に表れてきているのではないかと思います。
公益社団法人は、民間教育・塾の出来ること、塾の社会貢献を社会全体の教育プラットフォームの中に最大限に存在させて、民間教育の活動フィールドを堂々と広げていくと共に、その存在感を増していくことを思って活動します。
なぜならば、それが子どもたちと世の中の未来に明るく影響していくと思うからです。