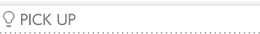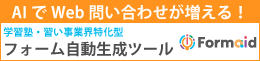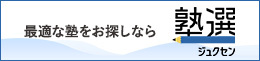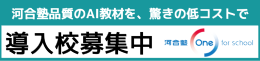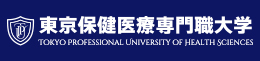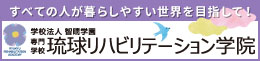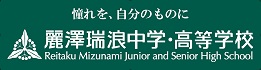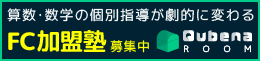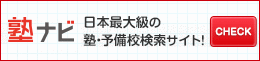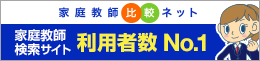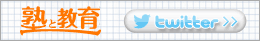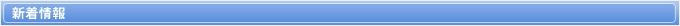
教育資源としての民間教育 第33回
公益社団法人 全国学習塾協会 安藤 大作 会長
個別最適化の教育は、民間教育に国費を支弁しながら進めるべき
教育環境においては、差し当たっての問題と本来の問題ともっと本来の問題の三つに分かれるように見ています。
差し当たっての問題は、新型コロナウイルス感染症対策を講じながらの教育ということです。これに関しては、学びの保証という意味での学校におけるオンライン教育や少人数学級の議論がそれに当たりそうです。第二波、第三波のことも見越しながらの解決策ということでテーマに上がります。
次に本来の問題として、個別最適化が挙げられるように思います。前述のオンラインこそ個別最適化ではないかという声も聞こえそうですが、それはもちろん対面集団授業の現在よりは個別最適化の色は強くなると思います。しかし日本の未来に向けて本来求められる個別最適化とは、飛び級の議論であったり、習得主義の議論であったり、いわゆる天才肌の児童生徒のキャリアパスであったり、もっと法整備に関わるほどの本質的な議論のはずです。このジャンルをしっかり議論し始めたときこそ、民間教育の出番ではないでしょうか?
学校教育だけではGIGA スクール構想が進んでタブレットが配布されたとしても、このレベルは学校だけでは完結しにくいはずです。むしろ義務教育は基礎学習を等しく保証していくことに主眼は置かれるべきですから、なおさら本質的な個別最適化は民間教育に国費を支弁しながら進めていくべきものであるかと思います。この時点こそ民間教育がしっかり声を上げるフェーズだと感じます。
そしてもっと本来の問題とは、自ら考え、自ら判断し、自ら行動する自立型人材の育成です。教育が世の中を作り、国や地域を支えるならば、本来の問題はここに行きつくのではないでしょうか?
これは塾、民間教育が関わる部分もあるでしょうし、入試が変わってこそという部分もあります。成長の様々な場面においての評価方法が変わり、また評価の必要性すら問われるかもしれません。
いずれにせよ、差し当たっての問題から順次議論して、解決に向かっていくのではないでしょうか? 日常の子どもたちの顔を見ながらの指導とともに、その子どもたちがずっと生きる世の中の仕組みも合わせて、目の前の子どもたちの幸せにつなげていってあげたいものです。