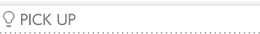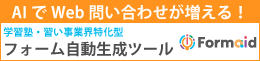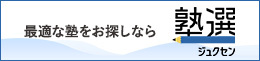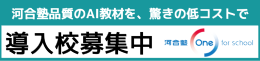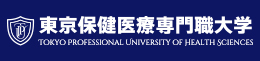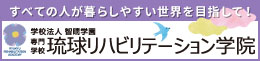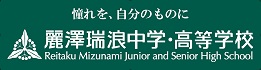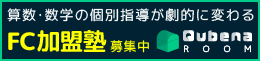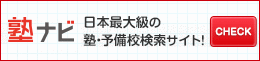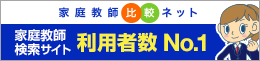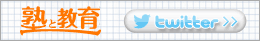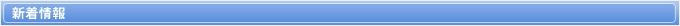
教育資源としての民間教育 第50回
公益社団法人 全国学習塾協会 安藤 大作 会長
AIやロボットでは到達できない、人間としての能力を育む
国会議員約200名、民間有識者約100名の教育立国推進協議会という超党派議員連盟。
その趣意書にはこうあります。
以下
日本は戦後、経済を中心に成長を続け、GDP 世界第2位の経済国として世界をリードする立場になった。しかし、1990 年以降、低迷する経済が続く中で、社会全体の活力が失われた。少子高齢化の急速な進展、長期化するデフレ経済、国際競争力の低下、新産業への対応の遅れが、国家全体に蔓延する不安感や危機感を大きくしている。(中略)日本の現在の政策の多くは、高度経済成長期を支えた方針のままであり、抜本的な改革が進んでいない。もし、今の延長線上に進めば、間違いなく日本は衰退国家になるだろう。
このようなパラダイムシフトにあっては、どのように時代が変化しようと、基本は「人」であり、日本がすべきは「教育立国」からというのが本協議会の設立の趣旨である。ただし、本会は国会議員のみで構成するのではなく、教育分野で先駆的な取り組みを行っている企業経営者、教育関係者を交え、その知恵を活かし合い、連動させながら進めていく。差し迫った危機を共有し、早急に教育改革を行うために協同して教育立国を実現する。(中略)
自分で考え、責任をもって、行動できる人材が必要である。マネジメントスキル、ホスピタリティ、クリエイティビティといった、AIやロボットでは到達できない、人間としての能力を育むことが重要であり、(中略)一人ひとりの能力が違うことを認め、それぞれの能力を引き出し伸ばすことがこれからの教育には求められる。
このように政治も含めて教育が大きく変わろうとしています。
ただ言うまでもなく、教育は現場の「様々な場面」という真実の積み重ねの上に存在しています。一方で安心して学べる社会環境があってこそ、その教育も存在し得るという現実もあるでしょう。これからは公教育の役割の再定義や民間教育への予算措置を含めた期待や役割も少しずつ明確になっていくのだろうと思います。
教育の明治維新のような改革の中で、これまでの塾や民間教育は新しい時代の中でどう期待されて、位置づけられていくのか、そう言ってもいいくらいの波とも言えるのかもしれません。
そのときにしっかりと私たち業界がこれまで何を為してきて、これからどういう役割をより一層果たしていけるのか、それが一層の社会貢献につながっていくことを主張して、民間教育は重要な社会資源という認識がさらに明確になっていけるように努めていければと思います。
公益社団法人全国学習塾協会を引き続きお支えいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。