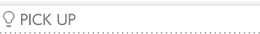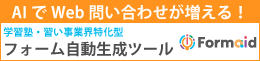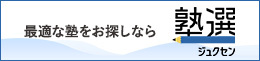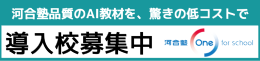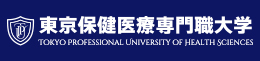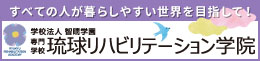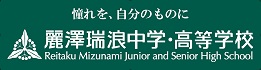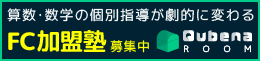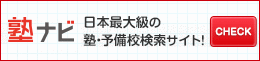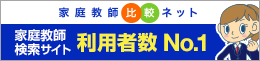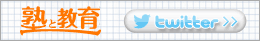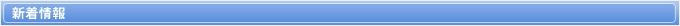
AJC(全国学習塾協同組合)森貞孝理事長の最新教育情報 第89回
三つ子の魂百まで
こども家庭庁が出来て、従来の縦割り行政が文科省、厚労省を中心にまとまってきたかに見える。これだけ出生数が減っていまさらと言えなくもないが、問題点も多い。2024年の出生数は、12月3日、68・5万人になる見通しとなった。遂に70万人を割り込む。コロナ禍で結婚や出産を控えた人が増えたほか、出産適齢人口がどんどん減少し続けていることも大きな原因だろう。国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計の中位推計で示された2024年の出生数に比べて7万人の下振れとなり、低位推計の66・8万人に迫る水準で合計特殊出生率は過去最低の1・15を割り込む見込み。そして出生数の減少に伴って、保育園の園児の減少から、今ゼロ歳児の保育が増え始めている。働く多くのお母さん方にとっては朗報かもしれないが、日本の家庭教育は累卵の危機にあるといえる。
昔から三つ子の魂百までということわざがあった。生まれてから3歳まで、昔は数え年だったから生まれてほぼ2年の間に身についた性格や考え方は100歳になるまで変わらないという意味だ。両親やたくさんの兄弟、祖父母など大家族の中で、教えられ、戒められ、耐えることを覚え、集団生活に慣れていく。そのような家庭教育が核家族にとって代わって子育てにあまり経験のない両親が、子育てよりも共働きで生計を立て、子どものためにではなく自分たちの老後のために生活設計を立てる時代。それが進んで生まれたばかりの子どもをゼロ歳児保育に預けて、仕事をする時代に進んできたというところか。ゼロ歳児の保育には、かなりの専門家たちが反対してきたのを知っている。親の愛情が、家族のぬくもりが一番大切な時に、仕事をしたい、収入を得たいという考えは間違っている。親子の絆、せめて孫と祖父母の絆をしっかり持つべきだ。という感覚が有識者の中には強かった。
教育は大きく3つの段階に分けられるという。
初めは生まれてから2、3年の時期。本能のままに生きていくのではなくて、生きるための知恵や集団行動、しつけ、物事の考え方を身につけるそういう時期、そして少しずつ家族の輪の外にも出て、社会を体験していくいわゆる保育の時期。
2つ目は長い間人間が生活していく中で身につけた知識を教わって知恵や学力を身につける時期。小学校から中学校までの学習の時期だ。学習塾はまさにその時期の子どもたちの学力をしっかり身につける部分に力添えをしている。
そしてそれらを基礎にさらに高度な研究を重ねて、今までにない新しいものを作り出したり、宇宙へ飛び出したりしていくというような技術を作り出していくのだ。
その一番初めの部分がなおざりにされていないか。次々に生まれてくる子どもたちが十分な家庭教育を受けないで、将来どのように成長していくことが出来るのか。
今不登校児童生徒が30万人を超えている。中曽根内閣の教育改革の時代から、日本は教育改革をする度にどんどん問題点が広がり続けてきた。これから20年後、30年後の日本を支える力になる子どもたちが世界に伍して、リーダーとして強い力を持つために、当面を糊塗していけばいいとは思わない。ますます少なくなっていく出生数を増やすことももちろんだが、未来の日本を担える力をしっかりと形作っていくのが我々に課せられた課題ではないのか。25年の年頭にあたって身を引き締めて日本の教育について考えてみたい。