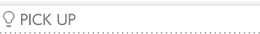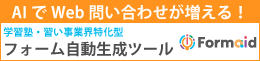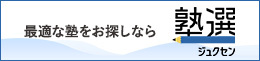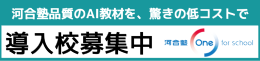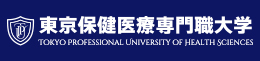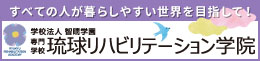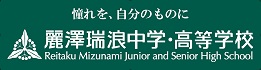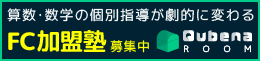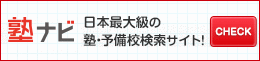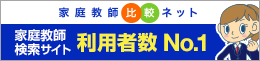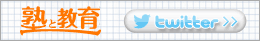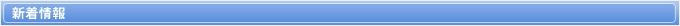
(株)塾と教育社 2024 秋季セミナー
Z世代からアルファ世代へ
顧客対象世代が変われば塾だって変わる!
11月10日(日)、東京都内の新宿住友ビル47階 スカイルームにて、株式会社塾と教育社主催(一般社団法人日本青少年育成協会後援)「2024 秋季セミナー」が開催された。テーマは「Z世代からアルファ世代へ 顧客対象世代が変われば塾だって変わる!」。
5つの講演と教材・コンテンツ紹介などが行われ、終日会場は賑わっていた。
ここでは、オープニングと5つの講演の要旨をお伝えする。
[オープニング]
Z世代からアルファ世代へ
顧客対象が変われば塾だって変わる!
PS・コンサルティングシステム 代表 小林 弘典 氏
顧客世代の変化は、学習塾業界において顕著であり、その変化には主に子どもと保護者の層の変化が関与しています。特に、保護者の変化が重要なポイントです。1995年頃、専業主婦から共働き家庭が増加し、これが学習塾の形態に大きな影響を与えました。この時期に、従来の集団塾から個別指導塾への移行が進みました。80年代中頃から個別指導は存在していたものの、その当時は小さな指導形態でしたが、95年頃から急速に普及し始めました。その背景には、共働き家庭が増えることで、保護者が学習塾に求めるニーズが変わったことが挙げられます。
集団塾から個別指導塾へのシフトは、机の配置やレイアウト、設備、さらには立地に至るまで多くの変化をもたらしました。特に東京のような都市圏では、個別指導塾が目立つようになり、従来の裏通りの小さな塾から立派な教室を持つ個別指導塾が増加しました。
今や学習塾業界において、個別指導塾の割合は全体の3分の2から4分の3を占めると考えられます。生徒数は個別と集団がほぼ同じくらいの割合ですが、それでも個別指導に対する需要は高まり続けています。このように顧客の変化は学習塾の運営形態を大きく変えており、今後の業界の動向にも影響を与えることが予想されます。
次に来る世代として、アルファ世代が注目されています。この世代は2013年以降に生まれた子どもたちであり、現在は小学校5年生程度です。彼らがメインのお客さん層になるのは、今後3~4年後のことです。その際、塾や教育のあり方が大きく変わることが予想されます。アルファ世代はデジタルネイティブであり、特にスマートフォンの普及が彼らの生活に深く根付いています。スマートフォンは08年に日本に上陸し、彼らが誕生した13年には普及率は62.6%に達しています。このため、彼らは他の世代とは異なる感覚を持っていると考えられます。さらに、アルファ世代は学校教育においてプログラミング的思考が導入されており、すでに一人一台のデバイスを持って学んでいます。
少子化が進んでいるため、将来的には中学生の人数が減少すると予測されています。現在、中学校3年生は107万人ですが、4年後には102万人、10年後には80万人となる見込みです。それと共に、彼らの世代が持つ特性や環境が変化しています。同時に保護者層も変化しています。Z世代の中には就職氷河期を経験した人が多く、彼らの親世代はポスト氷河期世代です。このような背景を持つ保護者が、アルファ世代にどのように影響を与えるかは不明ですが、オンライン教育の急速な普及が期待されます。
これにより、教室での指導内容や形態が変わってくるでしょう。従来のスタイルではなく、オンラインでの授業や個別指導が求められるかもしれません。また、偏差値重視の受験方法も変化するでしょう。子どもが減少する中で、基礎的な学力だけでなく、個々の特性を伸ばす支援が重要になると考えられます。さらに、広告宣伝の手段も変化し、教育の現場全体に影響を与えることになるでしょう。これからの教育や塾のあり方について、多くの変化が予想されます。
[講演Ⅰ]
チラシをやめても問い合わせ増?
保護者の獲得が得意 〜個太郎塾のシンプル戦略〜
株式会社 インパクト 代表取締役 井形 友幸 氏
チラシの効果が全くないと感じたり、ウェブ広告に挑戦してみたものの、結果が不明瞭で困っている様子をよく耳にします。最近も、チラシの効果が薄いという相談を受けました。LINE広告を試みたものの、成果が見えないとのことでした。これは、多くの塾で抱えている問題ではないでしょうか。特に、チラシの限界を感じつつも、ウェブでの効果的なアプローチがわからないといった声が多く聞かれます。
マーケティングの専門家として、成功するケースや失敗するケースが明確になってきたと感じています。特に、何も考えずに流行りの広告手法に飛びつくのは危険です。まずはGoogleを活用するなど、順序立てて進めることが大切です。
具体的な事例として、個太郎塾で行った試みを紹介します。個太郎塾は折込チラシをやめた結果、直営教室での問い合わせが18%増加し、入塾者数は30%以上も増えました。
以前はチラシやポスティングに多くの広告宣伝費を投じていましたが、最近はウェブ広告とMEO(マップエンジン最適化)にシフトしました。
チラシをやめてウェブに切り替えたいと思う経営者が多い一方で、なかなか勇気が出なくて二の足を踏んでいる方が多いのも事実です。切り替えが難しいと感じるのは、経営者やリーダーとしての立場を理解しているからこそです。現在の市場環境において、ウェブ広告の利用は避けて通れない選択肢です。そのためにターゲットを明確にし、適切なメディアを選ぶことで、より良い結果を得ることができるでしょう。
ウェブ広告とMEOにおいて、特にGoogleビジネスプロフィールはとても重要になります。Googleマップでの検索結果においては、順位や情報の内容が重要であり、特に教育機関の場合は、最新情報の更新や教室の写真のメンテナンスが不可欠です。塾の場合、ラーメン屋のように近隣の店舗に客を引き寄せるのとは違い、口コミや情報の充実度が、顧客の興味を引くためには大切な要素です。
だからGoogleビジネスプロフィールの内容を充実させなければなりません。さらに、ウェブ広告はチラシと同様の役割を果たし、スマートフォンでの広告表示が重要視されます。特にYouTube広告や検索時に表示される広告に力を入れ、SEO対策も行います。このように、顧客に的確に情報を届ける広告として、ウェブ広告とSNSを活用する方向に移行しています。
株式会社個学舎 代表取締役 金澤 匠時 氏(個太郎塾)
個太郎塾でチラシの効果測定をした結果、ウェブ広告の方が効果的であることが分かり、段階的にチラシを減らしていく決断をしました。しかしチラシを完全に廃止したのではなく、ウェブと連動させる形で活用しています。具体的には、QRコードを利用してウェブに誘導する仕組みを取り入れています。
そして直営校での効果を測定し、その結果をFC(フランチャイズ)オーナーに共有しています。また日々の反応率や取得単価をレポートで確認しながら、広告戦略の改善につなげています。直営校での成功をFCに広げることで、リスクを抑えつつ効果的な広告展開が可能になっています。
成功のためのポイントとして「選択と集中」が挙げられます。全体に薄く展開するよりも、一カ所に集中的に取り組むことで、効果をあげています。効果が出るまでには時間がかかることもあるため、じっくりと取り組む姿勢が必要です。
[講演Ⅱ]
これからの英検
新設級等英検Rを活用した英語力強化とは
公益財団法人 日本英語検定協会
英検協会は、財団法人として1963年に設立されました。昨年度の英検受験者数は約450万人で、通常の英検に加えて自治体向けの英検IBA(アイビーエー)や子ども向けの英検Jr.(ジュニア)も含まれています。協会の理念は、実用英語の習得と普及を通じて生涯学習の振興に寄与することです。設立60周年を迎えた協会は、理念に基づいた取り組みを続けています。
英検の2023年度までの総志願者数は1億3200万人を超え、日本の人口と同等の規模となっています。また英検の受験者の中では、中学生・高校生が約7割を占めており、特に高校入試や大学入試に向けて受験する傾向が見られます。英検は実用的な英語力を測るための試験で、複数のテスト形式を提供しており、最近ではコンピューターベースのテスト(英検S|CBT)の受験者も増加しています。
英検の魅力を三つ挙げると、まず、取得した資格は生涯有効です。
次に、受験者の実力に応じてステップアップできるシステムがあり、初めての方でも徐々にレベルを上げて挑戦できます。試験問題はリーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの4技能が出題され、3級以上は一次試験と二次試験があります。申込方法は個人申込と団体申込の二つがあります。英検の級は5級から1級まであり、準2級から2級へのステップアップは大きな壁とされていましたが、来年度から新たに準2級と2級の間に「準2級プラス」が設けられます。
三つ目に詳細な成績表(英検CESスコア)が提供され、合否だけでなく4技能別のスコアやCEFRも示されます。英検CESスコアにより、客観的に自分の英語力の位置がわかります、このスコアは各級ごとに合格基準スコアと満点が設定されており、例えば、2級では4技能の満点が2600点で1980点以上が合格とされています。受験者は自分の得意分野と苦手分野を理解し、より効果的に英語学習を行うことができます。
大学入試においては、外部検定試験の採用が増加しており、2024年度には462の大学が英検を含む試験を活用しています。(※1)特に一般選抜では英検の採用率が98%に達し、ほとんどの大学で入試に利用可能です。受験生の91.6%が英検を利用しており、大学入試においては出願資格や評価加算、合否判定の優遇、得点換算など多様な形で活用されています。東洋大学の事例として、英検CESスコア1980点以上で英語科目の得点を80点とみなす制度があります。(※2)特に2級を目指す受験生が増加している理由がここにあります。
準会場では、学校や塾の教室で試験を実施できるため、生徒にとっては通い慣れた場所で受験できるメリットがあります。準会場では一次試験の日程も柔軟に設定でき、検定料も本会場より安価です。特に2020年度から導入された一般受験者受け入れ制度により塾での受験が可能になり、受験の機会が広がりました。
この制度はコロナ禍におけるニーズに応える形で始まり、現在も多くの塾が一般受験者を受け入れています。この取り組みが評価され、保護者や受験生から好評を得ています。英検協会は、全国の塾と協力し、将来を担う子どもたちの英語能力向上を目指しています。模試や英語初期学習者向けのプログラムなど、多様な取り組みを進めており、今後も協会と塾との連携を強化していく方針です。
(※1)出典…旺文社教育情報センター
(※2)引用…2023年度東洋大学入試試験要項
※英検Rは公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
[講演Ⅲ]
Z世代の講師マネジメント
株式会社 Snmart WorX 代表取締役 渡邊 裕貴 氏
現在、Snmart WorXは全国で33の校舎を運営し、福祉の分野を含めて5つの事業を展開しています。私は大学院まで進学しその後、ITベンチャー企業に就職しました。ベンチャー企業で上場した経験から、教育とITの融合を試み起業しましたがうまくいかず、最終的には塾を開くことにしました。ミッションとして、塾での業務の効率化を図るためにテクノロジーを活用することでコストを下げ、労働時間を短縮しました。現在、アルバイト500名を抱える企業に成長し、昨年の売上は11億円、今年は13億円を見込んでいます。
Z世代の講師を効果的にマネジメントするためには、教育者としての視点だけでなく、商人としての視点も取り入れることが重要です。彼らが気持ちよく働ける環境を提供することが成功の鍵となります。
Z世代はリーダーシップを重視し、エンゲージメントを大切にします。納得しないと行動しない傾向があり、学業を優先するため、アルバイトで責任を持つことに抵抗を感じることがあります。また、インターネットの影響を強く受けて育っており、上の世代とは情報収集やコミュニケーションの方法が異なります。
実際に目の当たりしたケースとして、塾ではないですが新しい業態に移行した店舗がありました。その際アルバイトのマネジメントが崩壊し、上司や業態への不満、労働条件や給与の変更に対する不満が出ました。
立て直しのポイントとして、まずアルバイトでも優秀な人材がいることを認識して活用します。その次に私たちは決して偉そうにせず、彼らの話を聞き入れ、改善策を迅速に実行します。その際ダメなものはきちんと理由を説明し、リーダーが率先して嫌なことを行います。そして新しい店舗のコンセプトを理解してもらい、最低限のルールを設定し、評価項目を選定します。労基法に違反することは避け、ルールがないのにアルバイトに指摘することはしてはなりません。
講師採用に関しては、他塾の採用方法をよく比較して自分たちの採用方法を作ります。その際、昇給の評価基準を明確にし、褒めることを重視します。評価によって細かく昇給を行いますが、昇給するアルバイトとそうではないアルバイトをきっちり分けます。
教育者としての視点から商人としての視点にシフトし、ルールや決まりに基づいてマネジメントを行います。アルバイトへの依頼は理由とセットで伝え、労基法に違反することは避けます。このようにZ世代の特徴を理解し、彼らが働きやすい環境を整えることが、マネジメントの成功につながります。
[講演Ⅳ]
プロのコンサルタントが教える変化の時代に選ばれる秘訣
「変える?」or「変えない?」
オンリーワンの塾になるために
アイウィル 株式会社 代表取締役 小林 由香 氏
長年教育業界を見てきたコンサルタントとして、今ほど変化への対応を求められているときもないだろうと感じています。特に最近では、次々と新しい技術が生まれ教育のスタイルが急速に変化してきています。ギガスクール構想やICT教育など、時代の流れが速すぎてついていけないくらいです。正直、わたしはこの変化の速さにしんどさを感じているのですが、みなさんの中にも同じような感想をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。新しい教材やツールについては多くの方がお話しされているので、わたしからはあえて、やみくもに新しいものばかりを追いかけるのではなく、変えるものと変えないものを見極めて自塾のカラーを明確化することで、オンリーワンの塾を目指すことを提案したいと思います。
とは言え、時代の変化への対応は必要です。わたしは人事や人材育成を専門としていますので、教材やツールの進化ばかりではなく、特に指導スタイルの変化に注目しています。リーダー像の変化と言っても良いかもしれません。去年、夏の甲子園で慶應高校が優勝しましたが、慶應高校野球部のキャッチフレーズ「エンジョイベースボール」には驚きました。歯を食いしばって耐える時代から、楽しむことを重視したスタイルに変わってきているようです。昔はカリスマ監督や「オレについてこい」タイプの指導者が目立ったように思いますが、今では叱らない指導や自分で考えさせる指導が主流になり、リーダー像が大きく変わったなと感じました。同様に、昔と違って体罰なんてもってのほかで、言葉による指導の重要性も増してきていると感じます。Z世代やアルファ世代の子どもたちに対応するためには必要な変化でしょう。
その他で言うと、雇用や労務管理、コンプライアンスに対する意識の変化も見逃せません。サービス残業に対する世間の目は厳しくなっていますし、有給休暇の取得や最低賃金の上昇にも対応する必要があります。ブラックアルバイト問題も深刻ですが、最近は大学でも基本的な労働者の権利をしっかりと教えていますので、わたしたち自身がブラックとならないように注意する必要もあります。
ところで、変化への対応については一律ではなく、続けるものとやめるもの、変えるものと変えないものに分類して、続けるけれども変化を加えて進化させるもの、やめる代わりに何か別の方法を考えるなど見極める必要があります。何を続けて何をやめるかは塾によって違うと思うので、各塾が一度整理してみてほしいと思います。この作業によって自塾の立ち位置やウリがはっきりしてくるので、ポリシーを持って追求していけば、他塾との差別化にもつながると思います。時代の変化に対応しつつも、自塾のこだわりを大切にしてオンリーワンの塾を目指してほしいと思います。
[講演Ⅴ]
生徒がやみつきになる、特進館の有機的学習空間
「楽力」で学力を高め、集める塾から「集まる塾」へ
株式会社 ホットライン 特進館学院 代表取締役 北村 昌弘 氏
特進館学院は、ストレスを感じない環境を重視し、生徒や保護者、教員全てが快適に過ごせる教室作りに取り組んでいます。また、大手塾の情報力やシステム力を参考にしつつ、小規模塾のきめ細かさと安定感を兼ね備えた教育方針を採用しています。
●教育×エンターテインメント
今の時代は楽しむことが重要で、そのために楽しい環境を提供する塾を具現化しました。塾の広さは約1200平方メートルで、教室だけでなくフリースペースも充実しています。このフリースペースは、子どもたちが自由に勉強できる場所で、楽しい学びの場を創造することを目指しています。生徒が多く集まるように、楽しい雰囲気を重視し、壁を設けず開放感を持たせています。
塾には常時数名の正社員の先生がいて、子どもたちが自習する際にもサポートを行っています。特に受験生たちは学校の後に直接塾に赴き、長時間勉強をする生徒も多いです。最長で月に200時間勉強する生徒もいます。このように勉強時間を確保することが、成績向上につながると考えています。
また、塾内には様々な学習環境が整備されており、コンサートホールのようなスペースや高校生専用のエリア、タブレットを使った学習コーナーなどがあります。これにより学びを楽しむ空間を提供し、学習意欲を引き出す工夫をしています。来春には新しい校舎も稼働予定で、より多くの生徒に良質な学びを提供することを目指しています。
生徒の集客に関しては、集めようとするのではなく、自然に集まる環境を整えることが重要だと考えています。実績も出ており、志望校合格率も高く、多くの生徒が希望の学校に進学しています。また、大手塾の中に交じり、全国の英検プラチナパートナーとして認められるなど、信頼性の高い教育機関として評価されています。特進館学院は効率的な運営を目指し、無駄を省いた集約型の塾を目指しているのが特徴です。このように、楽しむことを基盤にした学びの空間を提供し、生徒たちが自主的に学ぶ姿勢を育てることで、優れた成果を上げているのが特進館学院の魅力です。
●デパート型運営
以前はコンビニエンスストアのような展開の塾を運営していましたが、集約型のモデルの方がいいのではないかと考えていました。一般的に、生徒が通う範囲は約1キロから2キロで、個別指導塾ではさらに狭くなる傾向がありますが、集団塾では2キロ程度まで広がることもあります。特進館学院では、25キロ離れた場所から通う生徒もいます。
小規模な塾では、生徒数が50人から100人程度で無駄が生じやすいです。また教員一人当たりの生徒数は、集団授業では一人の正社員の先生に対して約50人の生徒が適当だと考えています。塾の運営において、コンビニのような無駄の多い展開ではなく、デパートのように効率的な展開をしていきたいと考えています。
「ハート(情熱や愛情)」も大事ですが、それ以上に「ハード(物理的な環境)」が重要だと思っています。情熱や愛情は目に見えないため、実際に感じてもらうには、清潔な教室やトイレなどの物理的な環境が大切だと強調しています。特に長時間勉強する生徒にとって、清潔なトイレは重要であり、汚い環境ではどれだけ一生懸命教えても効果は半減してしまいます。
●失敗の先にあるセレンディピティとは
セレンディピティとは、偶然に珍しい宝物を発見する力や幸運を引き寄せる能力を指します。この概念は、幸せや不幸の関係についても考えを促します。つまり、幸せは偶然訪れるものではなく、その人の能力や考え方に依存しているというものです。例として、新薬開発の実験が挙げられます。失敗から新たな発見が生まれることが多く、これはノーベル賞受賞者にも見られる現象です。失敗を恐れずに追求することで、初めて成功への道が開けます。
教え子の結婚式に招待される理由は、単に知識や教え方の上手さだけでなく、心の支えになったという点にあります。教育の現場は変わりつつあり、個別塾や集団塾の枠を超え、どのように生徒と関わるかが重要になると考えられています。
これからの教育は、AIに取って代わられない人間らしさが求められ、そのためには生徒との信頼関係を築くことが大切です。さらに、教育サービスの質を高めるためには、ブランディングや差別化が必要です。生徒が集まる塾は、その理念や価値をしっかりと持っている必要があります。また少子化が進む中で、教育機関は生き残りをかけて新たなアプローチを模索しなければなりません。教育者は、単に知識を伝えるだけでなく、心の支えや成長を促す存在であるべきです。
最後に教育の場は、単なる知識の提供ではなく、心のサポートや成長を重視するサービスであり続けたいです。今後も変化する教育環境の中で、子どもたちから将来結婚式に招待されるような素晴らしい教師を目指していきます。











![[左] (株)インパクト 代表取締役 井形友幸 氏 [右] (株)個学舎 代表取締役社長 金澤匠時 氏](http://www.juku-kyoiku.com/wp-content/uploads/2024/12/2025_01_p69_chirashi.jpg)