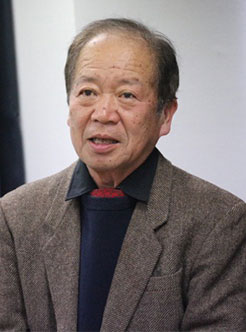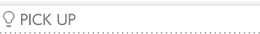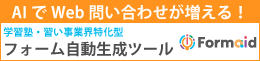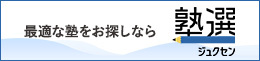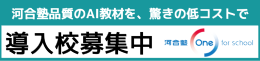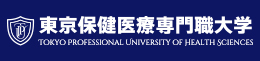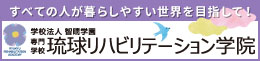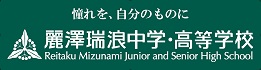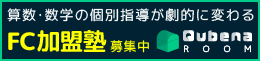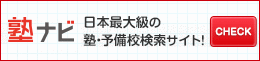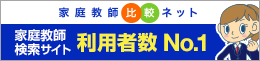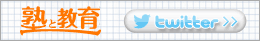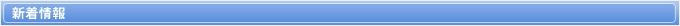
NPO塾全協 西日本ブロックで冬の勉強会
次の10年への戦略とSNSの力
2月27日、厚生労働省が発表した2024年の国内の出生数(速報値)は72万988人で過去最少。昨年は学習塾の倒産数も過去最多となり、業界にとっては厳しい状況が続いている。そんな状況を打開しようとNPO法人学習塾全国連合協議会(塾全協)西日本ブロックは2月16日、PS・コンサルティング・システム代表の小林弘典氏を講師に迎え冬の勉強会を開催した。個人や中小の塾が10年後も勝ち残るためにはどうすればいいか、業界の分析や今後の展望に加え新しい時代に対応していくための効果的な戦略とSNSの活用方法などを惜しみなく提供した。
急激に進む少子化10年後には少なくとも1.5万教場が消滅へ
人口動態統計や学校基本調査、特定サービス産業動態統計などから10年後の業界予測を立ててみました。2035年の18歳以下人口は405万人減の1395万人。学習塾は現在の約5万教場から最低でも1万5000教場は消滅するでしょう。この数字はかなり甘く見積もったものです。高校だけでなく大学すらも全入と言われる時代ですから通塾率も低下しますし、実際にはより深刻な状況だと思います。特に進学に特化した塾は存続が厳しいと言わざるを得ません。ただし、児童数の推移は地域によって異なるので、自塾エリアの状況はご自身で確認し、今後の対応を決めてください。(※表① 文部科学省・学校基本調査より)
考えられる10年後の「塾の姿」とは
さて、10年後も存続している塾はどんな塾でしょうか。受験塾・進学塾の多くは淘汰されますが、従来型の受験塾の中でも他の追随を許さない有力塾は勝ち残るでしょう。通塾率は世帯所得と相関関係があり、所得が高い程通塾率が高くなっています。現在の大学進学率は約6割。大学に進学しない層を考慮に入れると世帯所得650万円辺りが一つの境となり、高所得層を巡って塾同士で激しい競争が続くことが予想されます。中学受験は2015年頃から急激に増えてきました。ちょうど1971年~1982年生まれの就職氷河期世代の第1子が受験を迎える頃です。就職氷河期の中でも勝ち組となった層が中学受験に力を入れているため、この状況はあと2~3年は続くでしょう。売上上位160社の客単価をみると昨年は約50万円。コロナ流行期以降を中心に20年で10万円増加しています。非受験学年も含めた平均額ですが、この数字を押し上げているのが中学受験です。年間の費用が100~160万円かかる中学受験塾は珍しくありません。(※図①経済産業省・特定サービス産業動態統計より)
2つめが幼児、単科、特定の学校、フリースクール、サポート校、発達障害、留学支援など、スキマ需要を狙った特定分野の「進学専門塾」です。24年度の高校進学率は98.6%ですが、中学卒業後すぐに通信制高校への進学する割合が5.77%に上るなど、進路は多様化しています。中学生の不登校生の割合も6.71%と上昇していますが、最近はアスリートや芸能人、その他の目的があって通信制高校を選択するケースも多く、通信制高校への進学率と不登校生との相関関係はないようです。医歯薬系の進学に特化した専門塾があるように、多様化する進路に応じてより細分化されていくことでしょう。特に留学支援はより充実していくと思われます。人口が減少し、内需だけでは成り立たなくなる未来に親は子どもを海外に出すことを考えます。海外留学の斡旋業者は多数ありますが、海外の大学受験を専門とする塾はありません。海外の名門大学進学に特化した受験支援塾への需要は高まっていくと思います。
3つめは「とくい」を伸ばす「特化塾」です。今後は様々なことをそつなくこなすゼネラリストではなく、スペシャリストが求められる時代です。ここ数年、大学入試では総合型選抜の割合が増えました。現在は対策をすれば受かる状況ですが、今後はより難化してくるでしょう。大学が求める人物像が明確になり、スペシャリストを求める風潮が強まると個々の「とくい」=得意(または特異)を伸ばす塾が求められるようになるでしょう。
4つめは「近未来型の読み書きそろばん塾」です。高校や大学が全入できる時代がどのようなものか、入試を勉強の動機としていた層の意識がどう変わるのか、保護者の意識がどう変わるかは未知数です。「せめて人並みの学力を身につけて欲しい」と危機感を持つ人が学校以外でも学べる場として、基礎学力を底上げする塾があったらいいなというのは私の個人的な願望でもあります。
5つめは中高生版学童保育型「居場所塾」です。教員の働き方改革により部活動が減り、共働きの増加で帰宅後、家に誰もいない家庭がほとんどです。塾に「居場所」としての役割を求める方も増えてくるでしょう。他にも教育相談、子育て相談の場としての塾があってもいいと思いますし、公設民営塾は今後もなくならないと思います。
「次の10年」への戦略
先に挙げた1~4の塾はオンラインでも可能な点に人口減少地域は特に注意してください。デジタルの進化、発展がどのような変化をもたらすのかまでは予測も付きません。軍事用語に「適応は適応力を阻害する」という言葉があります。現状に適応しすぎていると結果的にその他の環境への適応力を下げることになるという意味です。短期的に「適応する」ということと、長期的な「適応力を上げる」ということの両方を意識することが重要です。何が流行り、どう変わって行くのか。周囲の変化に敏感になってください。社会の劇的な変化は塾にとってチャンスでもあります。大人も社会に適応すべく、新しいことを学び続けなければならないからです。対象を「子ども」以外に拡大することで市場は大きく広がります。まずはどの分野でも良いので地域でトップだと自他共に認めるものを持ち、それを軸に「10年後」の自塾の「塾の姿」を決定しましょう。そして余力のあるうちに一気に転換してください。戦力の逐次投入は却って不利になります。
集客とSNS
集客の原則は「客が客を呼ぶ」ことです。それは塾のように地域性が強い業種ほど顕著です。Webサイトには地域、塾生、学校名等、身近な話題で常に更新し内容を充実させましょう。ブログで読み応えのある記事をしっかりと書き、視聴しやすい数分の短い動画を作るのも効果的です。その際は塾生や保護者にみてもらうことを意識してください。その情報が塾生や保護者にとって有益であれば外部に広めてくれるからです。何の接点もない外部の人間がフラッとWebサイトに訪れることはまずないと考えてください。
新聞の購読率低下でチラシによる集客効果は薄れていますが、高校生へは校門配布が効果的なようです。地方紙の購読率が圧倒的に高い地域もあるため、自塾のエリアの特色をしっかりと見極めていただきたいです。また、単なる塾のチラシではなく、地域情報を載せたコミュニティ誌の形にすると読まれる確率が上がります。保護者サロンや無料相談会等、地域の方と日頃から接点を持つことも大変有効だと思います。自塾のファンを増やしていくことが集客へと繋がっていくのです。