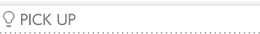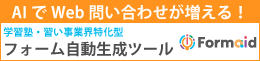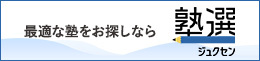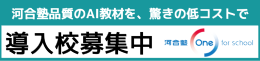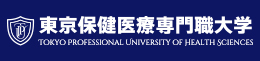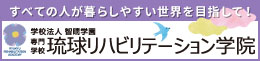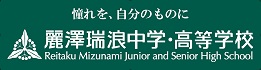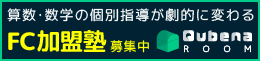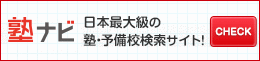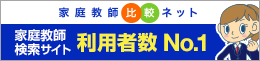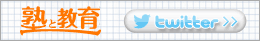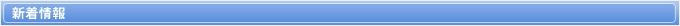
AJC(全国学習塾協同組合)理事長 森貞孝の最新教育情報 第8回
保護者に信頼される塾のみが生き残る
1月の初めに都立高校の校長先生とお会いした。地方の様子はどうですか。少子化の影響はかなり強く出ているようですねという話になって、「県庁所在地を除いては、話題は統廃合のことばかり。ひどい状況になっています」ということだった。
ここ2年、出生数の急激な落ち込みが話題になってきたものの、現中学生を抱えた地方都市で、今から大騒ぎをしている状況だ。公立学校でもそんな話ばかりが出る状況の中で、学習塾は生き残れるかどうかという厳しい戦いを迫られている。中学3年生が卒塾して生徒数が半減し、その埋め合わせが出来るかどうか、今年も塾が続くかどうかがカギなのだ。
その一方で、相変わらず他業種から塾業界に参入しようとしているケースも後を絶たない。
彼らが一様に言うのは、学習塾は初めに月謝を集めてそれで運営していけばいいが、他の業種は注文を受けて制作し、納品してから請求書を起こし、その翌月に手形で支払われたりする。受注してから入金するまでに最短2カ月、場合によっては5、6カ月かかる。しかも手形が確実に落ちる保証もないという。そういう世界からみれば、直接顧客と接して、取りはぐれのない業種は努力次第では非常に魅力があるのかもしれない。
新学期を迎える時期だ。1年の計画を立て本年の反省を踏まえて、来年のより良い結果を目標に、カリキュラムや指導体制を整える時期なのに、多くの学習塾は生徒募集に目の色を変えている。目の前のぐんぐん小さくなっていくパイをどれだけ囲い込んでいけるかに必死なのだ。
生徒の指導に心を砕くのは毎年のこと。その気持ちになるのは、新学期が始まって生徒数が落ち着いてからなのか。
よい指導をして、よい結果を出して、感謝され、生徒の気持ちに寄り添いながら成長していく若い生徒に大きな希望と目標を与え、彼らの人生に大きく影響を与える。そのような強い信念を持って塾業界に身を投じた教師たちが目先の生徒募集にあたふたしているのは、見るに忍びない。
今年の生徒募集が一段落したら、一度初心に立ち返って、塾の今後の方向性をきちんと立て直してみないか。今置かれている状況、長所、問題点、5年先の目標、地域での自塾のあるべき姿、そして教師陣の研修や教務のあり方など。
毎日の指導に追われて、なおざりにし、気が付いてみたら、1年1年追い詰められてあがきが取れなくなってしまうケースが多くないのか。
地域で多くの保護者に信頼され、頼りにされる塾のみが生き残る時代がすぐそこにやってくる。